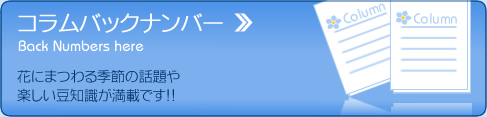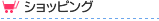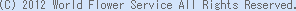花のギフト・プレゼントの通販トップ > 花コラム(季節の花の情報や旬の話題) > コラムNo.94

No.94 「2011年7月12日のコラム」
7月半ば・・・本格的な夏となりました!お元気にお過ごしですか?体調を整えて、暑い夏を乗り切りましょうね!
さて、夏の風物詩のひとつ「ほおずき市」が、あちこちで催される頃です。そこで今回は「ほおずき」の話。 「ほおずき」は東アジア原産、ナス科の多年草で、地下茎を伸ばして増やします。漢字では「鬼灯」とか「酸漿」と書かれ、お盆には提灯(ちょうちん)に見立てて飾られます。 「ほおずき」の名の由来には、いろいろな説があります。熟した実の果肉を抜いて、口に入れ鳴らして遊ぶことから「頬突き」。「ほおずき」を好む虫「カメムシ」のことを、「ホウ」ともいうので「ホウ好き」、などなど。 ところで、「ほおずき市」や園芸店などで販売されているものは、観賞用に日本で改良されてきたものですが、近年は食用のものが生産されています。かつて、口の中で鳴らした時のほろ苦さを想像すると驚きですが、ご安心ください!こちらはペルー原産の種で、糖度が高くフルーティな味と香りが特徴だそうです。スーパーなどで高級食材として注目を集めています。 「ほおずき」は6〜7月に、黄白色のナスの花に似た花を咲かせます。その後、5枚の萼(ガク)が袋状に発達し実を包み込み、初秋には実も萼もオレンジ色に染まります。 花言葉は・・・早熟・不思議・自然美・頼りない・いつわり。 「ほおずき」と一緒に、「風鈴」や「浴衣」や「うちわ」をそろえれば、熱帯夜も少〜し涼しくなりそうです!
|